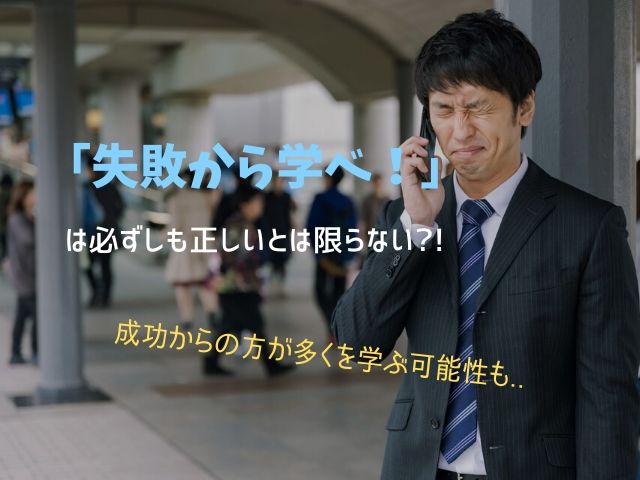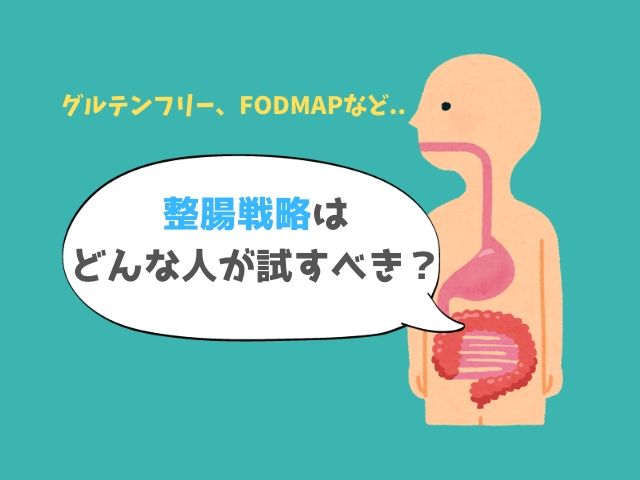赤羽(Akabane)
赤羽(Akabane)
目次
最新研究で判明「成長するには失敗から学べ!」は必ずしも正しいとは限らないみたい
「人は失敗からよく学ぶ」とはよく言ったものですが、どうやら最新研究によると、失敗から多くを学ぶためには重要なポイントがあるようです。
成長するには失敗から学べ?いや、成功から学べることの方が多いかもよ!という最新研究
参考になるのが、2019年にシカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネスが発表した研究(#1)で、人は失敗と成功のどちらから多くを学ぶのか?というテーマで大きく5つの実験を行っていました。
例えば1つの実験では、329名のテレマーケターを対象に10問のちょっとしたクイズに答えてもらって、彼らをランダムで次のようなグループに分類しました。
- 正解:最初の問題から数えて正解だった4問についてのみ「あなたの回答は正解でした」とフィードバックを与える
- 不正解:最初の問題から数えて不正解だった4問についてのみ「あなたの回答は不正解でした」とフィードバックを与える
ちなみに問題の中身は「アメリカの企業では、毎年どのくらいの額をお粗末な顧客サービスによって損失している? A. 900億円、B. 600億円」みたいな二択で、彼らの職業にかかわる内容で構成されました。
そして一旦、クイズの内容から気を逸らすために彼らが会社で残したインパクト大な経験について書き出してもらってから、改めてフィードバックをもらったクイズ4問についてテストを行いました。
するとここから、正解のフィードバックを受けた人で、不正解の場合よりも再テストの正答率が高いという結果(62% vs. 48%)が得られたんですね。
更に実験全体を通してみると、次のようなことも分かったようです。
- この現象は認知的に易しい問題でも見られて、問題の難易度は関係ないことが示唆された
- 1回目のテストで「再テストをやるよ。そこで正解するほどお金がちょっとずつもらえるよ」とインセンティブを与えた場合でさえ、失敗から学ぶ姿勢は成功よりも弱かった
- 不正解のフィードバックを受けた場合、その後に自分の回答を覚えていない傾向が確認された
まとめると、問題の難しさは関係なくて、不正解のフィードバックを受けた参加者らは失敗から学ぼうとせずに、むしろ頭の中から消し去るような傾向が見られた、と。これについて、研究チームも次のように仰っていました。
どうして失敗は学習効果を弱めるのか?失敗は自我を脅かすもので、だからこそ人々はその経験を頭から消し去ろうとしてしまう。実験の参加者らは、成功体験よりも失敗から多くを学ぶということはなく、しかし他人の失敗からは成功と同様に学びを得ていた。つまり、自我にまつわる問題が無くなれば、人は失敗から目を背けずにしっかり学ぶことができるということだ。[筆者訳]
ここから言えるのは、失敗を恐れる傾向が強い人や、失敗の代償がその人にとってデカい場合、その失敗体験は「消し去りたいモノ」になって頭に残りにくくなってしまうかもよ!ということ。
逆に、チャレンジ精神が旺盛だったり、自分のプライドを脅かすような失敗じゃなかった場合などは、その失敗から得られるモノも大きいんじゃない?と考えられるんですね。
注意点・まとめ
ただし注意点としては、まず今回の実験はイギリスとアメリカでしか行われていません。つまり、今回の結果がどこまで一般化できるか?は分からないということです。
とはいえ「成長するには失敗から学べ!」という誰もが頷く格言も、人や状況によっては当てはまらないかもしれないぞ、という可能性を示唆した点ではなかなか面白い知見だと言えましょう。
では最後に今回のまとめを見ていきましょう。
- 「成長するには失敗から学べ!」は必ずしも正しいとは限らない
- 5つの実験では、失敗のフィードバックを受けた人は成功のフィードバックを受けた人よりもその後の再試のスコアが低かった
- 失敗から学びを得るには、「失敗体験によって自我が脅かされている..」という恐怖感を取っ払う必要がありそうだ
こんな感じでしょうか。失敗から学ぶには失敗を恐れないチャレンジ精神が大事!ということでおひとつ。
 赤羽(Akabane)
赤羽(Akabane)
関連記事はこちらもどうぞ
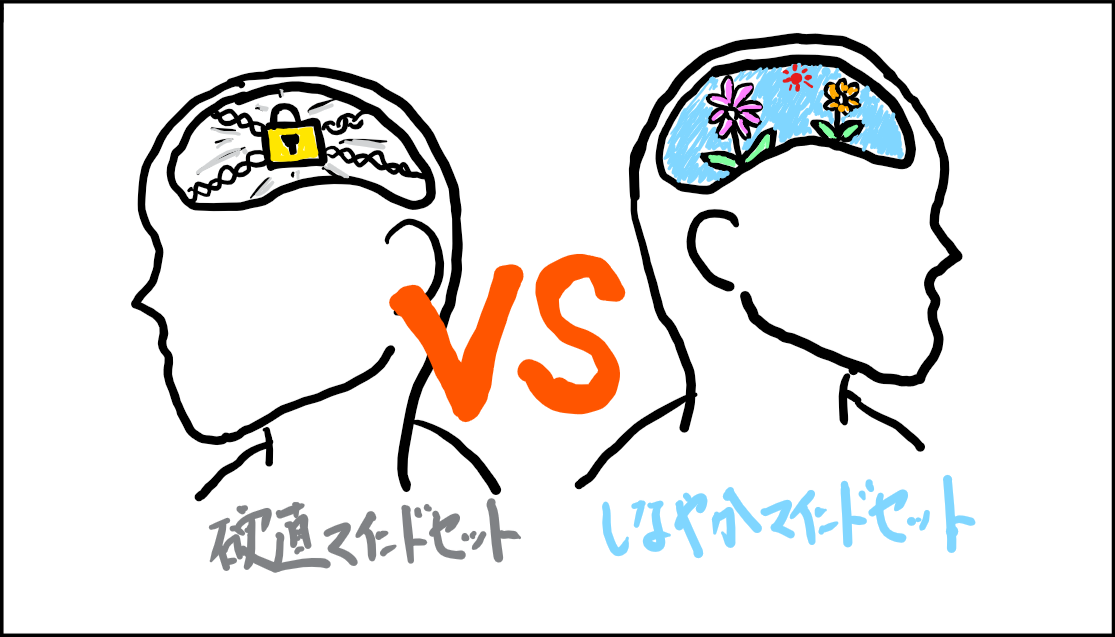 スタンフォード大学名教授が教える!成功する『マインドセット』とは?
スタンフォード大学名教授が教える!成功する『マインドセット』とは? 成功の重要ポイント「限界的練習」は世間が言うほどスキル上達に関係がない件。
成功の重要ポイント「限界的練習」は世間が言うほどスキル上達に関係がない件。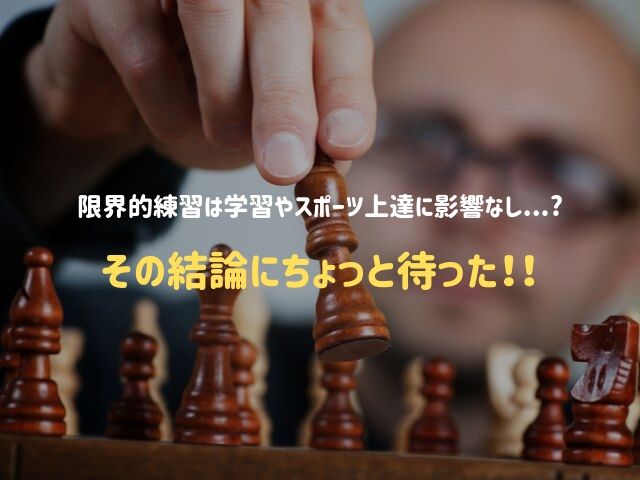 限界的練習はやっぱりパフォーマンス向上や分野での成功に大事な要素だ!という異論
限界的練習はやっぱりパフォーマンス向上や分野での成功に大事な要素だ!という異論
参考文献&引用
#1 Lauren Eskreis-Winkler, Ayelet Fishbach. Not Learning from Failure — The Greatest Failure of All. Academy of Management ProceedingsVol. 2019, No. 1.