 赤羽(Akabane)
赤羽(Akabane)
目次
“白か黒か思考”は誰しも陥る
白か黒か思考の人たちは、極端に物事を考えてしまいがちだ。これによって、彼らは現実を見ようとしなくなり、余計なストレスを感じるようになってしまう。黒か白のみの背景では本当の色は覆われるか、虚飾されるのみである。物事は白か黒かの二極で片付けられるほど明確なものばかりではないというのに。その間に灰色があることを心に留めておけば、人々はより真実の色に近づくことができるであろう。(#1)
詰まるところ、“白か黒か思考”とは“0か100か思考”とイコール。「一位になれないなら最初からやらないっすよ」みたいな考え方で、割と多くの人が陥りがちな思考かと。完璧主義とも近い感じがしますね。
・一回ミスをすると急にやる気をなくす人
・一番になれないならはなからやらない主義の人
・皆から好かれようとする人
・「いつも」「絶対」「全く」「最悪」「完璧」など極端な言葉を頻繁に使う人
ここで「別に考え方は人それぞれでしょう」と思われるかもしれません。確かにその通りなんですが、一旦最後まで読んでみて、それから一度考え直す機会を設けてみても遅くはなさそうです。
白か黒か思考が危険な理由
ということで黒か白か思考が私たちにどんな影響を与えるのか?という部分についてザックリ。まずは前回も紹介した驚きの結果から。
完璧主義は死に至る危険な思想である。
白か黒か思考はモノによっては「完璧主義」とも取れるので、この危険性もあるかと。簡単に言うと、完璧主義者は自殺願望を抱く傾向が強くて、実際に命を絶ってしまうケースもあったという信頼性の高い研究結果が出ているんですね。
ちなみにこうした結果になる原因には、完璧主義によくある「周りの目を気にする」傾向が根強いみたい。実際にこの元ネタの研究(#2)でも、
- 周囲から期待されてると思い込んだり、失敗を怖がるタイプの完璧主義は特に自殺の傾向が強かった
との報告が上がっていたり。つまり「失敗したら皆が見てる..馬鹿にされるんじゃないか..?」みたいな気持ちが強いとその分メンタルがもろくなって危険である、と。詳しくは以下の記事で紹介しています。
 「完璧主義」はメンタルを激しく病んで”死”に至る危険な思想である。
「完璧主義」はメンタルを激しく病んで”死”に至る危険な思想である。
白か黒か思考はパーソナリティ障害の全てのクラスターと強い相関関係が
そして白か黒か思考は他にもメンタルの病と繋がってまして、2012年の研究(#3)によると、白か黒か思考は全てのパーソナリティ障害のクラスターと相関があったのだとか。これは簡潔にまとめると以下のようなタイプに該当するということです。
精神分裂病質パーソナリティ障害..非社交的で他人に関心がない。
統合失調型パーソナリティ障害..思考がまとまらずハッキリしない。人間関係で孤立しがち。
境界性パーソナリティ障害..人間関係で不安定。感情のコントロールが難しい。
演技性パーソナリティ障害..他人の注目を集めるような派手な態度、外見を好む。
自己愛性パーソナリティ障害..自己愛が強く傲慢な態度を取りがち。
依存性パーソナリティ障害..他者に過度な依存。選択や決定権も他者に頼る傾向。
強迫性パーソナリティ障害..一定の秩序を保つことに強い固執。几帳面すぎ、完璧主義。
正直この境界線はハッキリしませんが、白か黒か思考は上記のような傾向に強く当てはまったのだとか。また黒か白か思考を持っていなくとも、黒か白か思考を好ましく思っているだけでも上記のB、Cタイプと相関がみられたとのことで、注意が必要です。
 赤羽(Akabane)
赤羽(Akabane)
関連記事はこちらをどうぞ
 【ビッグ5性格診断】死に至る思想「完璧主義」に陥りがちな人が持つ2つの共通点とは?
【ビッグ5性格診断】死に至る思想「完璧主義」に陥りがちな人が持つ2つの共通点とは?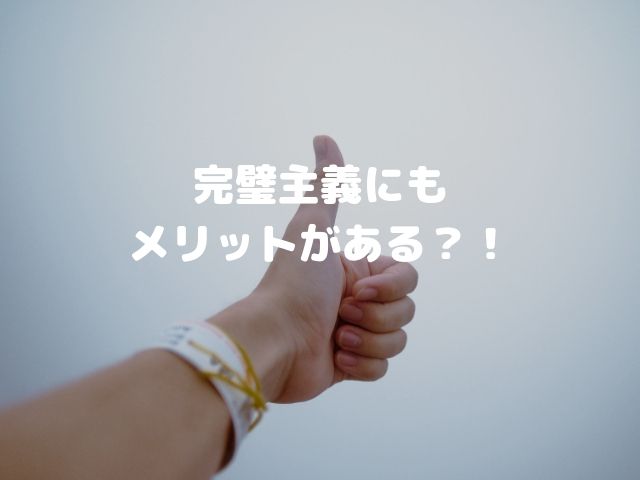 【一筋の光か】完璧主義は短所ばかりではない?!実はこんなメリットがあるかもしれない。
【一筋の光か】完璧主義は短所ばかりではない?!実はこんなメリットがあるかもしれない。
参考文献&引用
#1 Sravanti Sanivarapu,”Black & white thinking: A cognitive distortion“,Indian J Psychiatry. 2015 Jan-Mar; 57(1): 94.
#2 Smith MM, Sherry SB, Chen S, Saklofske DH, Mushquash C, Flett GL, Hewitt PL,”The perniciousness of perfectionism: A meta-analytic review of the perfectionism-suicide relationship“,J Pers. 2018 Jun;86(3):522-542.
#3 ATSUSHI OSHIO,”An all‐or‐nothing thinking turns into darkness: Relations between dichotomous thinking and personality disorders“,Japanese Psychological Research2012, Volume 54, No. 4, 424–429.



